 0
0 
多摩川クラシコの明暗に見る、呪縛としての「自分たちのフットボール」

「何かがあったわけではない」(?)
3月30日に行われた川崎フロンターレとFC東京の『多摩川クラシコ』。日本代表の森保一監督に名波浩コーチ、大岩剛U-23日本代表監督も勢ぞろいした注目度の高いゲームは、それにふさわしい白熱の接戦——というわけにはいかなかった。
結果は3-0で川崎Fの勝利。MF脇坂泰斗のゴールで先行した川崎Fが、FC東京のGK波多野豪を退場に追い込んだ後に2点を追加しての快勝だった。川崎Fの視点でこの試合を観れば、最高の内容とまでは言えないにしても、最高の結果を得たのは間違いない。そう感じられる試合だろう。
一方、FC東京の視点で言えば、満足できる要素は一つもないのではないかという試合展開であり、結果である。
試合後、ピーター・クラモフスキー監督は「最初の60分から70分までは何かが多くあったわけではなかったと思います」と振り返ったが、実際は「失点」という重要な「何か」が起きていた。
0-1のビハインドを負いつつも、「自分たちのフットボールを続けていけばまた流れが来て、報酬が返ってくると思って戦いを続けていました」と、特に改めることなく「何かが多くあったわけではない」戦い方を継続。結果として90分を通じてシュート4本(うち、枠内1本)という低調な「自分たちのフットボール」を貫徹することとなった。
ゼロトップvsオーソドックス

この日、FC東京の布陣は快勝した前節・アビスパ福岡戦を踏襲したもの。10番タイプの荒木遼太郎をいわゆる“ゼロトップ”気味に配置し、その脇に松木玖生を置くシステムを含め、前節の成功体験を継続しようという意図を感じさせるものだった。
ただ、ここからして疑問ではある。前節に“ハマった”形は「自分たち」が上手くやったから、適切な組み合わせだったからという以上に「相手」があっての結果。福岡と川崎Fはまるで違うチームであるので、二匹目のドジョウがそこにいるとは限らない。
対する川崎Fが選んだのは「変化」だった。今季初めてボランチを2枚置く4−2−3−1のシステムを採用。守備は4−4−2で固める日本では非常にオーソドックスな守備戦術なので、日本の育成を経てきた選手たちにはなじみ深い守り方である。試合後、川崎Fの選手たちからは、それほど多くの準備時間を割いたわけでなくとも共通理解を得やすかった旨の発言が相次いだのも自然なことだった。
連敗中の川崎F・鬼木達監督は「ここまでの戦い方を考えた中で、システムのところも含めて考えなければいけないというところに至っていました」と転換の理由を話す。
これに加えてもう一つ、FC東京に対したときに、実効性のある守備ができるのはこちらだという感触もあったからだろう。試合後、FC東京の荒木が「対策してきた相手に自分たちがどうするかができていなかった」と率直に振り返ったように、荒木が活きるスペースを消す効果も間違いなくあった。
鬼木監督がもう一つ強調したのは「気持ち」の要素。単なる精神論、あるいは球際のプレーでのガッツという面だけではなく、受け身の守備で簡単に失点するシーンが目立っていた今季の川崎Fには重要な要素だった。
DF三浦颯太が「相手のウイングがピン止め(SBとCBの間に立って守備側の選手の動きを制限するプレー)してきたけど、(相手のウイングを)後ろに置いてでも前向きの守備ができた」と振り返ったように、守備ラインを高く保つといった集団としてのベースに加え、個々の守備判断も強気に機能する場面が際立っていた。
川崎Fの選手たちも認めていたように決して万全の試合内容ではなく、FC東京の拙攻(せっこう)に助けられた部分も大いにある。ただ、3連敗中だったチームにとって、勝利に優る薬はない。今季取り組んできた形を変える決断を下したからこその「自分たちのフットボール」がこの日の川崎Fにはあった。





















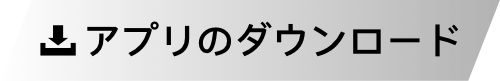


 リンク
リンク
 連絡先
連絡先


